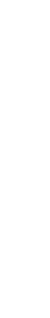Rabbit うさぎ

うさちゃんはストレスに弱いのです。ストレスも様々ですが、主なものとして
恐怖:ウサギは被捕食動物ですから臆病です
痛み・痒み:病気など
不安:引越し・通院
その他:暑さ・寒さ・運動不足・かまい過ぎ
これらの要因により、交感神経の緊張を招き、ストレスがさらに持続するとステロイドが過剰に作られます。その結果、免疫力が弱くなる可能性があり、ウサギ特有の慢性的な感染症につながります。
うさぎの代表的な病気
下記の他に、歯ぎしり、胃痛、腹痛でうずくまっている、ガスがたまってお腹が張っている、便の量が減るなどの症状があれば、小さな動物ですから症状が重くなる前に早めに受診してください。 治療が遅れると、肝リピドーシス(脂肪肝)になって手遅れになることが少なくありません。
歯科疾患・眼科疾患
家ウサギの主食はあくまで乾草(牧草)です。もちろん野生のウサギは繊維質で茎ばかりの雑草を食べています。牧草の食べる量が少ないと噛む回数が減るので、歯が摩耗せず、歯の噛み合わせが悪くなり(不正咬合)、口腔粘膜や舌を傷つけ、その痛みで食欲が低下します。
一方、歯並びの悪さは涙を排泄する鼻涙管を圧迫、閉塞させ、涙流症(涙やけ )、涙のう炎をおこします。
胃停滞胃毛球症
ウサギはよくグルーミングをするので、少量の毛玉が胃の中にあるのは普通のことです。この毛玉は少しずつ、牧草の繊維質とともに胃を通過していきます。牧草の摂取が少なかったり運動量が少ないと、大腸の働きが不活発になり、胃の中にたまって増えていく毛玉で胃の容量は減少し、少し食べただけで、すぐに満腹になってしまい食欲は低下します。
消化管閉塞
牧草の食べが少ないと食物繊維が不足して、布やカーペット、畳をかじることが増えます。これらは消化されない繊維のため、腸閉塞になってしまいます。
盲腸便秘
食物繊維の摂取不足は大腸の運動性を悪くして便秘を引き起こします。
関連するコトブキ通信
検診について
聴診、触診、検便、口腔内検診(不正咬合、口内炎など)などを行います。うさぎは、歯及びお口の状態が健康を左右すると言っても過言ではないペットです。ぜひ定期的に検診を受けてください。併せて食事指導も行います。
Guinea pig モルモット

野生のモルモットは、野草の茎や根、樹木の皮などの、ビタミンCが豊富で繊維質の物ばかり食べています。おうちで飼育しているモルモットも同様で、牧草を与えます。
牧草の食べが悪いと咬む回数が減るので、歯が磨耗せず咬み合わせが悪くなり、舌や口腔粘膜を傷つけ(口内炎)、その痛みで食欲が減退します。 またビタミンが不足すると、コラーゲンや象牙質、セメント質が十分に作られなくなり、皮膚が弱くなったり、虫歯になったり、さらに歯の咬み合わせも悪くなったりします。
健康を維持するための食事方法
ご自宅では、牧草70%、ペレット10%、野菜(ビタミンCの多いもの)20%を目安に与えて下さい。ビタミンC不足に陥ると、コラーゲンや象牙質、セメント質などが作れなくなり、歯が悪くなる原因になります。また、モルモットはウサギと同様に歯が常に伸び続けます。常にこのことを考えてあげてください。牧草が足りないと、歯が磨り減りません。歯が伸びすぎてしまったら、早急に相談してください。
更に遺伝として「不正咬合」というケースもあります。食欲はあるのに食べにくい、だから食べない。虫歯も問題です。その他、舌の潰瘍、頬粘膜の潰瘍などができて痛くて食べが悪い、口臭、口周りの毛が唾液で汚れる、胃腸の運動が悪くなるなどの、様々な症状が出ることがあります。モルモットが健康な生活を送るためには、食事には細心の注意を払わなくてはいけません。
検診について
聴診、触診、検便、口腔内検診(不正咬合、口内炎など)などを行います。モルモットは、歯及びお口の状態が健康を左右すると言っても過言ではないペットです。ぜひ定期的に検診を受けてください。併せて食事指導も行います。
Ferret フェレット
フェレットの主な病気
インスリノーマ

インスリンを分泌するすい臓のβ細胞の腫瘍で、高インスリン血症によって低血糖状態になり、嗜眠・虚脱・腰フラ・震え・発作などの症状がみられます。フェレットのインスリノーマは他の臓器への転移は少ないですが、再発しやすく、完全な回復は期待できないことが多くあります。
フェレットは飢餓状態、敗血症、肝疾患その他、腫瘍で低血糖になることもありますが、インスリノーマが代表的な原因です。 インスリノーマの疑いがある場合は、外科手術時にすい臓の検査をして確認します。
インスリノーマの特徴
- 4~5歳で発症することが多い
- メスよりオスが多い傾向がある
副腎疾患
フェレットの副腎疾患のほとんどが、犬の副腎疾患と違い、脳下垂体の異常のない副腎腫瘍や副腎増殖性疾患です。副腎ホルモンではなく性ホルモンが上昇して、脱毛や雄の排尿困難、雌の外陰部腫脹、腹部膨満、食欲不振などが起こります。その原因はいまだに明確になっていません。治療は内科的治療と外科的治療の併用があります。
Hamster ハムスター

ハムスターは地中生活に適応するため、身体はずんぐりして足も尾も短いです。左右2つの頬袋があります。夜行性で地中生活に適応する動物です。乾燥地帯の砂漠に生息している種類が多く、過酷な環境に適応するために冬眠する野生では、昼間は深い穴の中で寝ており、夜になると食事を求めて一晩10kmの距離を動いていると言われています。
ゴールデンハムスターでは、臭腺が腰部に一対黒色で出ています。ジャンガリアンハムスターでは、腹部と口角に臭腺があり、胃は前胃と後胃に分けられます。
ハムスターの種類
ゴールデン
ハムスター
| 体重 | 130~210g |
|---|---|
| 妊娠期間 | 15~16日 |
| 産仔数 | 1~15頭 |
| 離乳 | 18~21日 |
| 寿命 | 2~3年 |
ジャンガリアン
ハムスター
| 体重 | 30~45g |
|---|---|
| 妊娠期間 | 18~21日 |
| 離乳 | 18~21日 |
| 寿命 | 2年 |
ロボロフスキー
ハムスター
| 体重 | 15~30g |
|---|---|
| 妊娠期間 | 18~21日 |
| 離乳 | 18~21日 |
| 寿命 | 2年 |
飼い方について
ゴールデンハムスターは原則として個別飼育となります。ジャンガリアンハムスターをはじめとするドワーフハムスターは、多頭飼いが可能です。
1床材
ゲージの床に敷く材料は乾草かペーパータオルが良いでしょう。木製チップ、オガクズはアレルギー皮膚炎の原因になることがあります。
2温度
1日の温度変化が10℃以上あると体調に影響を与えますので、温度管理に注意しましょう。
3飲水
主食がペレットの場合は必ず飲水を与えます。飲水が不足すると、食欲が低下したり、尿路結石等の病気になりやすくなります。
4歯
切歯の伸びすぎを防ぐために、小枝や板等を与えましょう。
ハムスターの主な病気
蟯虫症(ぎょうちゅう症)
一般に無症状で、重度感染で軟便・下痢が見られます。
トリコモナス症
一般に無症状で、重度感染で軟便・下痢が見られます。
不正咬合
先天的な下顎の成長不全やゲージの咬み癖が原因です。
ニキビダニ症
母親から仔に伝搬し、生涯皮膚に常在しています。ストレス、栄養不良等で発症します。
アレルギー性皮膚炎
床材、食事等のさまざまの原因で発生します。
泌尿器疾患
ウサギ同様、正常でも色のあるおしっこをします。疾患がある時は、茶褐色~茶白濁色の粘稠性の高い(粘り気があり濃い)尿になります。
膀胱炎
赤色尿が見られます。尿検査で細菌、潜血等を確認します。
尿路結石
結石はカルシウムを主成分とするものが多くあり、赤色尿、頻尿、排尿障害などの症状がみられます。重症例では元気消失して死亡する例もあります。結石の疑いがある場合は、レントゲン検査を行い結石を確認します。
結膜炎
アンモニア臭や異物による刺激、切歯の根尖病巣が主な原因です。またハムスターは全身の状態が悪いと両眼に眼ヤニが見られます。
腫瘍
高齢のハムスターに発生します。治療は、外科手術が望ましいです。
Little bird 小鳥
小鳥の主な病気
腱はずれ(ペローシス)

セキセイインコ、スズメに多くみられます。股関節・膝内節・足根関節が腫脹することで靭帯が弱くなるため、常に開脚した状態になり、歩くことも止まり木に止まることもできなくなります。生後2~3週間以内に処置しないと完治はできません。
原因は、親の栄養(ビタミン、カルシウム、リン、マグネシウムなど)不足が代表的です。その他、遺伝・落下・転落などが原因のケースもあります。
早期であれば両脚を正常位置に戻した状態でテープ固定します。しかし、発見が遅れることが多く、その場合は根治をさせることよりもその形のまま生活させていく工夫をします。開脚したままでも鳥はよく適応して暮らしていきます。